仕事の社会的役割と会社の新しい挑戦について学習
中学生が会社訪問
(2009/11/22)
日本はさまざまな資源を海外から輸入しています。
現代社会に欠かせない資源を安定的に確保、輸入して、それを全国のすみずみまで供給する仕事は大変重要な役割を担っています。中でもエネルギー資源は供給不足が許されません。
資源を輸入して精製・製品化し、販売している会社はどのような考え方を持ち、どのような仕事をしているのだろうか。
生徒たちはまず、海外から膨大な量の資源を輸入、それを計画的に製品化して販売するプロセスの説明を受けました。すべてのプロセスにたいへんな時間と労力がかかっています。
輸入量は想像もつかない規模ですが、私たちの生活を維持させるための重要なお仕事です。
しかし資源には限りがあります。
海外で安定的に調達するという責任とともに、いかに無駄なく効率的に生産するかの工夫努力も重要だと教えていただきました。
苦労して遠くから運んでくる資源の大切さを一番実感している皆さんのストレートな気持ちが生徒に伝えられました。
会社としての画期的なチャレンジについても紹介されました。新ビジネスがスタートしているのです。
時代の変化に合わせて柔軟に、そして果敢に新しい分野に挑戦する民間企業のエネルギーに満ちた取り組みです。生徒たちは記念すべき時期に立ち会ったのです。早くから新しいビジネスの可能性に着目、継続して研究開発をしてきた研究者の地道な努力、それを支えてきた会社全体の協力が実を結んだ事実を知りました。
企業のダイナミックな現在進行形の姿を体感する学習プログラムでした。

資源の有効利用(エコフィード)にも注目
高校生が飼料会社で学習
(2009/11/14)
日本全国で毎日生産される飼料の安定供給が、私たちの「食」を支えています。
このほど高校生が飼料会社を訪問、飼料生産の工夫努力、社会的な役割について学習しました。
生徒にとって飼料に関するお話はすべて初めて知ることばかり。
例えば、水産飼料は、種類によって原料が異なるだけでなく、水中での溶け方や浮き方にも工夫がなされていて、食べるのに時間をかける魚貝の飼料はすぐに溶けてしまわないような加工がなされています。
食べやすいように魚の成長に合わせて大きさを変える飼料もあります。
畜産や養魚の生産者は早く、大きく育てることを重視するため、適量の餌をきちんと食べさせる必要があります。ただし畜種によって味やにおいの好みに違いがあるので、食べさせるためには好みの飼料にする工夫が必要になるそうです。
飼料工場が食品のリサイクル機能を持つことも知りました。
飼料の原料の一部に米ぬか、おから、パン粉、ビール滓などの食品副産物を使用しています。
食品工場などから発生する食品残さを利用した飼料(エコフィード)への取り組みも期待されています。
飼料工場は資源を有効利用する機能も持っているのです。
次代を担う生徒たちには、これからの日本の食糧問題を真剣に考えていくことが求められます。食を支えるという大きな役割を担うビジネスの学習をすることができました。

社会との信頼を大切にする経営姿勢
高校生が訪問学習
(2009/10/11)
企業が社会の一員として事業活動を続けるためには社会に対する責任を果たし、社会との信頼関係を築くことが大切です。
訪問した企業では早くからCSRへの取り組みを開始、国内外の事業所でISO14001認証を取得して環境対策を充実させているほか、乳がんの早期発見・診断・治療の大切さを訴えるピンクリボン活動も応援しています。
「お客様相談センター」では、お客様から届いた、商品についての問い合わせや苦情、要望の声を大切にして、それらに親身になって丁寧に対応すると共に、商品の改善や新しい商品の開発に生かすという姿勢を持ち続けていることを学びました。
生徒にとって、企業がこのような活動を行っているのを知るのは初めて。商品を通じてしか知らない企業のCSRを通じた真剣な姿勢に触れることができました。
企業のCSR。高校生にとって企業を学習するための新しいテーマになりそうです。

生徒はネットセキュリティにも強い関心
個人情報の扱いなど学習
(2009/7/28)
学習に同席すると、多くの企業でネットの安全利用、マナーについて触れていただいています。
ある企業で生徒が一様に身を乗り出したのは、ネットでの個人情報取り扱いの注意について。
些細と思う情報でもいくつかの情報を組み合わせ、絞り込んでいくと特定の個人にたどりつくことがあることを知った時です。
また、自分たちは小さな携帯やパソコン画面の中での限られた者同士の会話と思っていても、実は世界中から見ることができることを知った時。
生徒によってネットセキュリティに対する意識にはかなりの開きがありますが、それでも生徒全員が驚いていました。
「遠く離れてしまった親友たちとの交流に活用しています」。
ネットの持つ機能を有効、有意義に使う子どもたちに、具体的な事例による安全教育の重要性を実感しています。

手作り&デジタルの仕事を学習
修学旅行の中学生
(2009/6/12)
今もグルメマップ、カーナビなど私たちの生活を便利で楽しいものにするために多くの生活シーンで利用されています。
最近では衛星を使った精密で見やすい地図も作られています。
このほど、地図をより身近で利便性の高い「情報」として制作する会社を中学生が訪問しました。約50年にわたり地図作りをしてこられたわが国有数の専門会社です。
GISを利用して便利な情報を搭載した付加価値の高い地図情報、立体化したレリーフ地図、海や空の地図などさまざまな地図制作について学習しました。いずれも高度な技術と豊富な経験が必要です。
また、地図は過去と現在の橋渡しもしてくれます。
過去の地図と現在の地図をパソコン上で重ね合わせると、自然・地形や地名、住居などの人々の生活の変化がタイムスリップしたように理解できます。
地域を理解するための面白い学習方法です。
時代が変わっても地図作りの根幹部分は、繊細な人の手による仕事であり、現場を観察する地道な仕事であることを知ったことも学習成果です。
そして何よりも、地図大好きな社員の皆様の溢れる情熱に触れられたことは一生の思い出になりました。

中学生が研究者から直接授業
仕事のやりがいも学習
(2009/5/9)
人間の作業や行動を補助したりする人間共存型ロボットや、人が行動すると危険な場所で人に代わって働く無人システムを開発しています。
二足歩行するロボットを間近で見ながらロボットについて説明を受けました。
ロボットは歩くだけでなく横になったり、立ち上がったり、踊ったりと実に様々な動きができます。
バランスよく立っているだけでもロボットにとっては大変なことだということです。
生徒は研究者の方からこうした動きを可能にする、コンピュータプログラム、カメラやセンサ、関節部分、モーターなどロボット構造について分かりやすく説明していただきました。
ロボットに使用されているパーツなども触ることが出来ました。
一つ一つが日本の最先端技術の塊です。そしてこれらの総合力こそが自動車同様に日本のロボット開発が世界をリードする理由でもあります。
ロボット開発の仕事に就いたきっかけや仕事のやりがいについて、研究者の方の熱いお話も聞くことができました。
生徒にとって先端技術に触れる貴重な機会になりました。
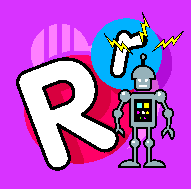
厳しい製品管理と最新システムに驚き
バーコードの大切な役割も発見
(2009/4/26)
個人情報も扱いますし、仕事の流れやシステムそのものがノウハウの固まりだからです。
このほど中学生が訪問した施設も一般には公開していないところです。
輸入された製品が国内各地の利用者のもとへどのように配送されるのか。
そして配送されるまでの製品の在庫や厳重な品質管理、個々の発注に正確に対応するためのシステムなど「精密」な管理がなされています。
見学した生徒も、製品を包装して発送するところ、という認識が一気に変わりました。
建物全体に配置された最新システムと共に、熟練した皆様の真剣な確認作業と製品の丁寧な取り扱いの様子に圧倒されていました。
毎日使っている製品が実はこれほどまでに数多くの過程と、多くの人の確認、管理の手間をかけて送り出されて手元に届くことが分かりました。
一連の作業では、パッケージについたバーコードが大切な役割を果たしていますが、生徒がその機能を初めて目撃した瞬間でした。

いろいろな機会に次世代に伝えたい
メーカー本社で学習活動実施
(2009/3/28)
都内の機械メーカーを中学生が訪問しました。
ものづくりの素晴らしさと、会社組織、部署の役割についての学習を本社会議室で行いました。
メーカーでの学習は従来から工場見学というイメージがあります。
しかし工場は立地場所の関係で見学できる生徒や機会が限られ、
最近は管理、セキュリティ面でも見学できる施設が少なくなっています。
でも、ものづくりの素晴らしさや喜びなどの魅力を多くの次世代に伝えたい。
そうした機械メーカーご担当者の思いで実現しました。
生徒は会議室で冒頭から機械の一部を見ながら説明を受けました。
最初は何の機械か分かりませんでしたが、解説を通じて同社技術の結晶だということが分かってきました。
小さな機械が持つ高い機能(役割)とその用途を解説していただきました。
そして世界中でこの製品が使われて高く評価されていることを知りました。
事業案内ビデオでさらに会社のお仕事についての理解が深まりました。
生徒たちは、2時間の学習を通じて日本のメーカーの高い技術力やものづくりの素晴らしさ、皆さんの熱い思いに出会いました。
技術者の方の「あっと言わせたときの喜び」も学びました。

食品会社の社員の皆さんの熱い思いと努力を学習
仕事のやりがいも
(2009/1/28)
当日は急遽社長が学習会に参加されるサプライズがありました。
終始分かりやすい説明で想像以上に厳しい食品の製造管理システムを知るなど、すばらしい学習ができました。
毎日利用する食品が多くの人たちの思いと最新技術の両輪によって生産され、流通していることを理解しました。
製品がお店に並ぶまでのすべての製造・流通プロセスを管理しているそうです。これによって美味しくて安全な製品が提供できます。最新システムによってほとんど人が触れることなく生産され、さらに厳しい検査を経て出荷されていることなどを具体的に説明していただきました。
美味しく安全な食品を作りたいという生産現場の専門家のお話を聞くこともできました。また、環境にやさしく安全な食品製造のため、生産工程で出る資源を有効利用して野菜も生産しているそうです。
最後に「会社が大きくなった秘訣は?」という質問をした生徒たち。
難しい質問。でも、それに答えて「新鮮でとても美味しかった、というお客さんの声が仕事をしていて何よりもうれしい」という社員の皆さんの明るく真剣な言葉が返ってきました。
この変わらぬ思いと努力こそが会社が成長した最も大きな原動力だということを、生徒も理解できたはずです。

中学生が新商品開発のプロセスを学習
食品会社本社で
(2009/1/5)
ある食品会社を訪問した中学生は、同社で商品開発のプロセスを分かりやすく説明していただきました。ロングセラー製品を数多く抱える会社のお仕事の学習です。
商品開発の部署は会社内の他の部署と連携しながら、売れる商品を開発する重要な部署なのです。市場調査を経て、多くの人による試食など新商品の試作のための調査と改良を繰り返します。味はもちろん、価格、パッケージデザイン、キャラクターなどを考えます。
さらに発売された後も、消費者の購入情報や評価を参考にして改良を積み重ねます。一つの商品が大変な努力によって生み出され、育てられているのです。
中学生は、商品が多くの準備と工夫・努力、そして常に改良を行ってロングセラー製品に育てられていくことを学習しました。
